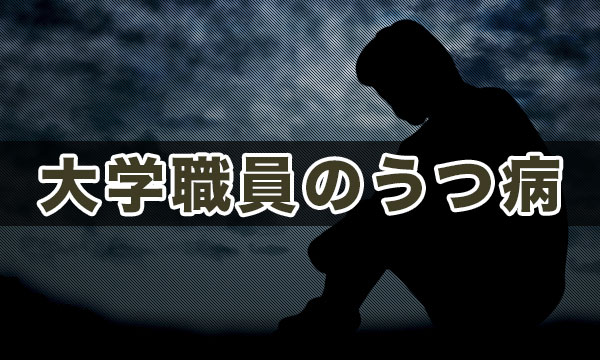一見、大学職員の仕事は、学校で働く仕事なので平和なイメージがあるかもしれませんが、実際にはパワハラが存在します。
大学職員もパワハラを受けることは普通にある

大学職員は、準公務員的な見方をされることもあるので、健全な労働環境が整えられているように思うかもしれませんが、実際はそうではありません。
大学職員の間でも、当然のようにパワハラは起きています。
しかし、パワハラが起きても対応できない場合があるのです。
パワハラ防止対策の部署も全く機能しない
大学によっては、パワハラ防止対策のための部署が備わっている学校もあるかもしれません。
例えば、人事部のような部署が、パワハラ防止対策の担当をすることもあります。
しかし、そのような部署があろうとも、パワハラを止められないこともあります。
権力を持つ教授によるパワハラ

一つは、です。
このような非常に力のある教授が、パワハラを起こした場合は、いくらパワハラ対策の部署を設けても、対応しきれないことがあります。
なぜならば、対策の部署で働く職員よりも、パワハラを起こす教授の方が立場が上だからです。
特に、主任教授クラスになると、一般職員では対応が難しいことがあります。
どうも学校現場では、「職員よりも教授の方が位が高い」というカースト制度的な意識も根強いため、大学職員の方が教授に気を使っていることも多いのです。
ですから、特に主任教授クラスがパワハラをすると、いくら対策部署を設けても、誰もパワハラのことについて指摘できないことが現実にあります。
立場が上の職員によるパワハラ

もう一つは、役職が付いていたり、非常に権力のある大学職員(学長、学部長、課長など)によるパワハラの場合です。
このように、一般職員よりも立場が上の職員によるパワハラの場合は、もし注意をするとので、なかなかパワハラを指摘できないのです。
理事長、もしくは学校創立者と深い関係のある職員からのパワハラは、たとえ対策部署を備えていたとしても、誰もパワハラについて注意できないことがあります。
休日出勤も当たり前?残業代も請求できない?
パワハラが行なわれているかどうかは、配属する部署によって、全く違ってきます。
パワハラが行なわれる部署だと、強制的に休日出勤させられたり、また残業しても残業代が請求できないこともあります。
さらに達が悪いのは、それをあたかも自主的に行ったかのように仕向けることです。
上司が精神的に追い込み、従うようにさせて、部下がこき使われる現場があります。
自主的にしているように見せかけているため、何か問題が起きたときも、自分たちの責任にならないように仕向けることができるでしょう。
何か質問してもひたすら無視される
例えば、何かわからないことがあり、質問してもひたすら無視されることもあります。
もしくは質問したら、「そんなこともわからないのか」と叱責や罵倒を受けることもあるのです。
仕事の仕方がわからず、質問もできないので、仕事はなかなか進みません。
すると今度は、仕事が進まないことに怒られるのです。
質問もできず仕事が進まない、進まないのでまた責められる。
このような負のスパイラルのパワハラが、大学職員の現場でも起きています。
水さえも飲ましてもらえない
私の場合は、職場で水さえも飲ませてもらえませんでした。
夏場にどんなに喉が渇いても、水の一滴さえも飲ませてもらえません。
つまり、基本的な人間の生活が送れない、違法状態でした。
それだけ悲惨なパワハラが大学職員にもあるのです。
パワハラを知っていながら、見て見ぬふりをする
また、職員の誰も対応できないようなパワハラは、
他の職員も、なんとなくパワハラが起きていることを知っていながら、権力関係で自分ではどうすることもできず、見て見ぬふりをする職員も少なくありません。
つまり、パワハラを受けている職員からすれば、「自分のことを見殺しにされている」と感じることでしょう。
大学職員の現場は、人間関係もドロドロしていて、権力による制圧も少なくありません。
また、このようなパワハラは、外部には漏れないように内密にしていたりもします。
大学職員という職業は、決して楽な仕事ではなく、内部では相当きついことが起きているものなのです。
パワハラを指導と履き違えている
また、上層部の人間の中には、パワハラを指導と履き違えているものもいます。
人材育成のための指導と銘打てば、パワハラのような追い込みをしても良い、もしくはするべきだと、勘違いしているひとも少なくありません。
特に、自身もそういう偏った指導を受けた人間ほど、自分にも部下ができた場合は、同じようにしようとする傾向にあります。
こういう人間が上層部に立つと、たとえ部下が精神的に、肉体的に追い詰められたとしても、自身の責任を問うことはないでしょう。
倒れるまで働くのが当たり前かの風潮
一般的な企業ではありえないことだと思いますが、実は「倒れるまで働くのが当たり前かの風潮」が大学にも存在します。
「倒れて病院送りになって一人前」という非常に偏った認識をしている上司も中にはいるのです。
そんなことをしていると、本当に働けない体になる可能性があります。
敢えて体を壊してまで働く必要はありません。
しかし、そういう非常に偏った上司の下につくと、倒れるまで働かなければならないことがあります。
不運にもパワハラ対象になった場合は耐えるしかない

配属された部署でパワハラ被害に遭い、他の職員が何も対応してくれないときは、パワハラを受けているひとは、職場を辞めない限りはひたすら耐えるしかありません。
そうやって、パワハラ被害を受けて精神的に病み、半ば強制的に辞めさせられたひとはたくさんいます。
大学経営も決して安泰ではないので、上司にも余裕がない
また、今は少子高齢化で生徒獲得も難しくなってきています。
つまり、大学経営自体も決して安泰ではなく、上司も役員から厳しく言われている可能性があります。
なので、上司自身にも余裕がなく、そのしわ寄せがパワハラとなって現れるのかもしれません。
指導力がない上司ほど、部下の状況を顧みず、高圧的な態度をしがちです。
そういう上司は、部下がどうなろうとも、一切責任を負わないことが多いのです。
そもそも今の職場で働き続ける意味はあるのか
もし、反旗を翻して行動を起こすならば、労働基準監督署などへ通報することです。
どこまで対応してくれるかわかりませんが、ある程度の対応は取ってもらえる可能性もあります。
また、大学は保守的なところも多いので、一度大きくパワハラ問題が取り上げられたら、対応せざるおえないかもしれません。
労働基準監督署などに相談すると、「自分の立場が危ぶまれるのではないか」と思うかもしれませんが、そもそも今の職場でパワハラに耐えて働き続けることが、本当に意味あることでしょうか。
無理に耐え続けて、いつか体を壊してしまう可能性も十分ありえます。
今現在、パワハラに苦しんでいる大学職員は、学校内部では対応しきれないこともあるので、ハローワークや労働基準監督署などに相談してみると良いでしょう。
パワハラ被害に遭い、泣き寝入りしているだけでは、次の被害者を出しかねないので、